
ママさん
同じ人なのに子供とか大人とかで
免疫機能が変わるの?
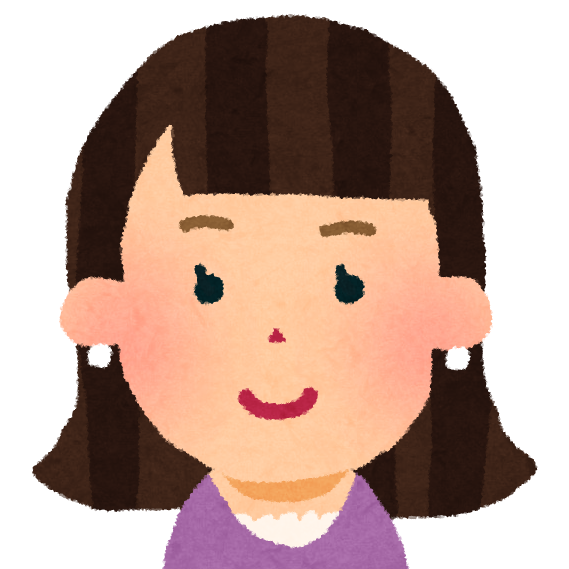
それが 免疫がライフステージで大きく
変わるらしいのよね。
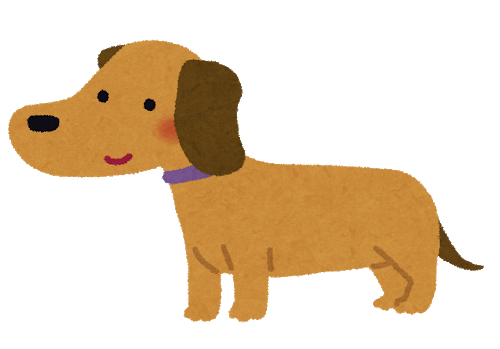
それじゃ それぞれの年齢に合わせた
免疫で気をつける事があるんだね。。
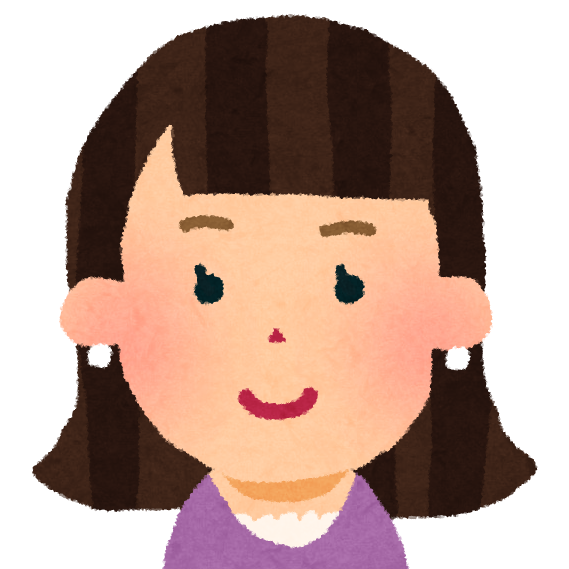
さすが クウさん
理解が早いわね。
今からライフステージ別にお話ししていきましょう。

いつも クウさんばかり
さすが!って言ってもらえて
いいな。。
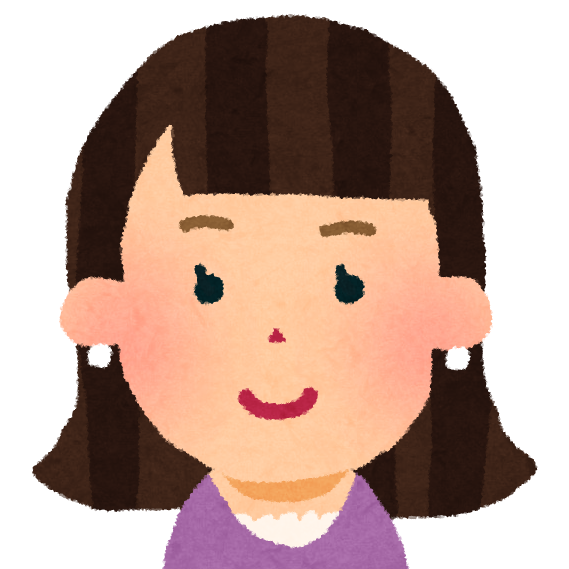
ララさんも
すごいわよ!
さすが!さすが!

まったく なんだから。。
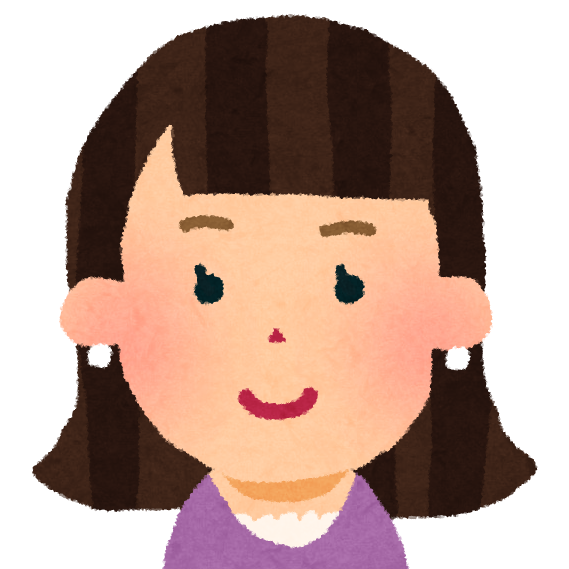
それでは始めましょう!
免疫は私達の体を最近やウイルスなどの
病原体や癌細胞といった異物から守って
くれるからね。

胎児期ー学童期
赤ちゃんは生まれる前、胎盤を通じて母親から免疫を受け取っています。生まれてからは母乳や予防接種などで感染から守っています。
妊娠中や出産、授乳を通して赤ちゃんに免疫が受け継がれる事を母子免疫と言います。母から赤ちゃんに移行する抗体を移行抗体と言われ、赤ちゃんにとって大切です。また移行抗体は2種類あって、妊娠中胎盤から移行する方法と生まれてから母乳から移行する方法があります。
●出産時に受け継ぐ免疫
妊娠28週以降、母の免疫は胎盤を通して赤ちゃんに移行されます。この時、大切なのがIgG抗体です。唯一胎盤を通過できる抗体で、細菌などの異物を排除する働きがあります。生まれた時には、母と同じレベルのIgG抗体を持っているのです。妊娠中にワクチン接種すれば、その抗体が赤ちゃんに移行するのです。

●母乳を介した免疫
母乳からの移行抗体で重要なのは、IgA抗体です。これは母乳に多く含まれ、特に初乳に多く含まれています。IgA抗体は腸の粘膜で、細菌やウイルスの侵入を防ぎ、体の粘膜を保護する働きがあります。
また 母乳は赤ちゃんの腸内環境を整えるのに重要です。母乳にはオリゴ糖やラクトフィリンのような腸内環境を整える成分が多く含まれています。生まれて間もない母乳栄養児はビフィズス菌を多く含み、善玉菌が多く、免疫機能が発達しやすいと言われています。
母乳は3種類に分かれます
1)初乳;産後1-3日、IgA抗体や免疫成分が豊富
2)移行乳;産後4-14日、蛋白質と免疫成分が減少し、糖質、脂質が増加
3)成乳;産後14日以降、成長に必要な栄養素や糖質、脂質が豊富

予防接種による免疫獲得
母から受け継いだ移行抗体は生後3-6か月で減少。それに合わせて定期的な予防接種を受けて、免疫を獲得していきます。
母子伝播
母親の胎内にいる細菌が赤ちゃんに受け継がれる事を母子伝播といいます。経膣分娩では、赤ちゃんが産道を通る時、母親の細菌に接し、母由来の細菌を獲得する事ができます。母由来の腸内細菌は赤ちゃんに定着しやすく、腸内環境をつくるのに大切なのです。
年齢別発育
1歳過ぎ
離乳後は、母からのサポートではなく、自分で免疫が発達し始めます。4-5歳ころまではよく風邪をひきますが、そのことで細菌などの抵抗力を身につけます。大人に近い状態になるのは 小学校入学する6歳ごろと言われています。
学童期
10歳前後になると、免疫にかかわるリンパ型(胸腺、扁桃、骨髄など)が発達し、強い免疫機能を獲得します。とくに胸腺は病原体を排除する働きのあるT細胞を作るので、胸腺の発達は免疫維持に重要です。胸腺の発達は思春期がピークです。

スキャモンの発育曲線

青年期ー成人期
この時期は いろいろな病原体と接するので十分抗体を獲得し、免疫機能を維持できる時期になります。しかしこの時期は生活の乱れやストレスの多い時期でもあります。細かく見ていきましょう。
生活習慣の乱れ
免疫細胞はたんぱく質やリン脂質、コレステロール、ミネラルからできています。活動のためには糖質、活性化させるのにビタミン、ミネラル。免疫機能をきちんと働かせるにはバランスのよい栄養が必要です。
●たんぱく質、ビタミンの不足
ダイエットなどをしていると、蛋白質の不足が。蛋白質は免疫細胞や抗体の材料に、ビタミンは免疫機能をサポート、とくにビタミンAは粘膜の健康維持に必要です。
●脂質、糖質の摂り過ぎ
炭水化物ばかりを摂っていて、肥満になると脂肪細胞が肥大化してアポトーシスを起こします。そこに免疫細胞が集まり、炎症反応を引き起こします。
また 動物性脂肪の摂り過ぎは、肥満になるばかりでなく、自然免疫の働きを阻害し、免疫機能を低下させ炎症反応を引き起こします。
このように炎症反応が慢性的に続くと、免疫機能が過剰に活性化して、正常な細胞や血管を傷つけてしまい 動脈硬化などの原因にもなります。
●腸内環境の乱れ
腸は食べ物や飲み物と一緒に細菌なども侵入しやすい器官です。そのため腸には免疫細胞が集まって病原体の排除しています。腸内環境が乱れると、栄養の吸収や代謝の低下ばかりでなく、免疫細胞の働きも低下してしまいます。
●アルコール摂り過ぎ
過剰な飲酒で血中アルコール濃度が上がると、病原体を攻撃処理するNK細胞やマクロファージの働きを低下、B細胞やT細胞などにも影響してしまいます。肝臓でアルコールを代謝の過程でできたアセトアルデヒドも多くなると免疫細胞を傷つけてしまいます。

ストレス
青年期は心身の発達に伴う変化、成人期は仕事や家庭、経済などの原因でストレスを感じやすい時期です。
●自律神経の乱れ
自律神経は交感神経と副交感神経からなり、相反する働きをします。例えば 交感神経が優位だと顆粒球は多くなるが、副交感神経は少なくなるという感じです。ストレスを感じると交感神経が刺激され、戦う活動の方へシフトします。
交感神経が優位になると、副腎髄質からアドレナリンがでて顆粒球が増え、体内の常在菌を攻撃してしまったり、新陳代謝が促進しすぎて 過剰に免疫反応がおこったりします。リンパ球は低くなり、T細胞の不足で免疫機能が低下します。活性酸素が増え、正常な組織を攻撃したり、副腎皮質からコルチゾールが過剰に分泌され、免疫機能を低下させます。血行が悪くなります。

●喫煙
たばこに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、自律神経のバランスを見だしてしまいます。その他にも有害物質が免疫機能に影響。また血管を収縮して、血流を悪くし、全身に免疫細胞が行きわたりにくく、免疫の低下につながります。

性ホルモンとの関係
●男性ホルモン
男性ホルモン、テストステロンは免疫を抑制し、炎症を抑える働きがあります。男子は自己免疫疾患になりにくく、感染症にかかりやすいと言われています。男性ホルモンは女性ホルモンより減少が穏やかなので、更年期以降は女性より免疫が低下しにくいと言われています。
●女性ホルモン
女性ホルモン、エストロゲンはB細胞を活性化しIgG抗体やIgM抗体の産生を促し、エストラジオールは樹状細胞を活性化し、免疫を高める働きがあります。女性は感染症に対する抵抗性は強く、過剰な免疫反応をおこしやすく自己免疫疾患に罹りやすいと言われています。更年期になるとエストロゲンが減少し、体調をくずしやすくなるようです。
もう一つのホルモン、プロゲステロンは免疫を抑制する働きがあります。プロゲステロンが増える排卵後から月経前は免疫力が低下します。子宮は妊娠準備に入るため、一時的に免疫機能を低下させ、受精卵を異物として排除しないようになっています。

壮年期ー老年期
年齢を重ねると免疫機能の低下、60代で20代の半分と言われています。感染しやすく、重症化しやすいのです。
免疫細胞の老化
免疫細胞は骨髄にある造血幹細胞から作られています。年を重ね、造血幹細胞の機能が低下すると免疫細胞が減少し、働きも鈍くなります。
●T細胞の老化
T細胞は胸腺で作られ、思春期を過ぎたら、機能は低下、40代でも新生児の1/100と言われています。T細胞は特定の異物を認識して免疫反応を活性化し、体内の病原体や異常細胞を排除、免疫のバランスを保つことで体を守る中心的な働きをしています。T細胞の減少で、感染しやすく重症化しやすくなります。また自己を見分ける働きがあるので、T細胞の働きが悪くなると自己免疫疾患に罹りやすくなります。
●B細胞の老化
年を重ねると骨髄の造血能力も低下。B細胞が減少します。B細胞が低下すると細菌感染症に罹りやすくなります。またB細胞はIgA抗体を作るので、機能低下でIgA抗体が低下して腸内フローラの乱れが起こります。
●NK細胞とマクロファージの老化
年を重ねるとNK細胞の機能が低下、異物を攻撃し排除する働きが弱まり、感染症やがんにかかりやすくなります。他にも老化細胞の除去などおおくの免疫機能に関係しているので、影響は大きいです。マクロファージ機能の低下は異物を取りこみ、分解するペースが落ち、感染症やがんへの防御能力の低下につながります。

参考;ほすぴ

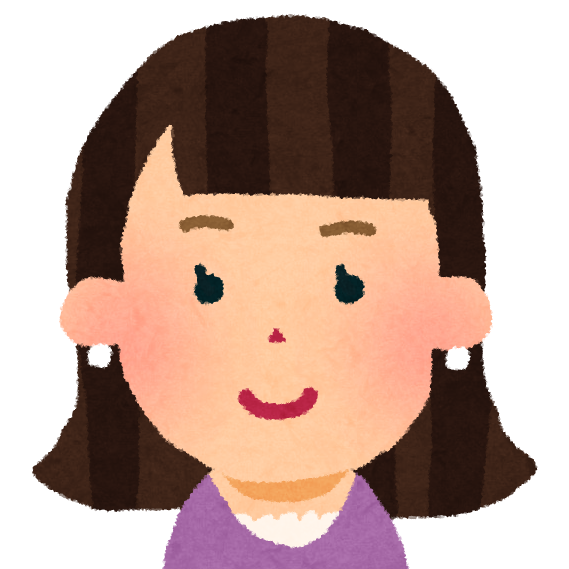
アレルギーが増えている背景に免疫が関係しているとか。。
アレルギー患者増加の背景に、衛生仮説があると。。
現代の子供は昔の子供より環境中の微生物に触れる機会が減少、
その清潔すぎる環境とアレルギー患者の増加と関係あるという説です。
この説の中心はヘルパーT細胞、ヘルパーT細胞は細菌、ウイルスでは
ThI細胞へ、花粉、ダニはTh2細胞分化します。新生児の時は皆、Th2細胞が優位で、細菌などにふれTh1細胞が増加します。この二つはお互いのバランスをとって免疫が機能されています。過剰に衛生にするとTh1細胞が成熟せず、Th2細胞が優位になりアレルギー疾患にかかりやすくなるというのです。
適度に微生物に接する事は免疫を発達させるには大切です。

投稿者プロフィール
- 東京都在住。
薬剤師、健康管理士など
趣味;ヨガ、自然の中にいる事
最新の投稿
 薬膳2025.11.26冬にお勧め缶詰メニュー
薬膳2025.11.26冬にお勧め缶詰メニュー 健康管理士2025.11.06免疫をライフステージ別にみてみましょう
健康管理士2025.11.06免疫をライフステージ別にみてみましょう 健康管理士2025.11.05免疫を高めるには
健康管理士2025.11.05免疫を高めるには 健康管理士2025.11.02免疫とがんの関係
健康管理士2025.11.02免疫とがんの関係



